婚姻届を提出するのは人生の大きな節目のひとつですが、「ふたりで一緒に出すもの」というイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし近年では、さまざまな事情から「ひとりで婚姻届を出す」というケースも増えてきています。本記事では、その割合や理由、注意点などを詳しく解説していきます。
婚姻届をひとりで出す割合の実態とは
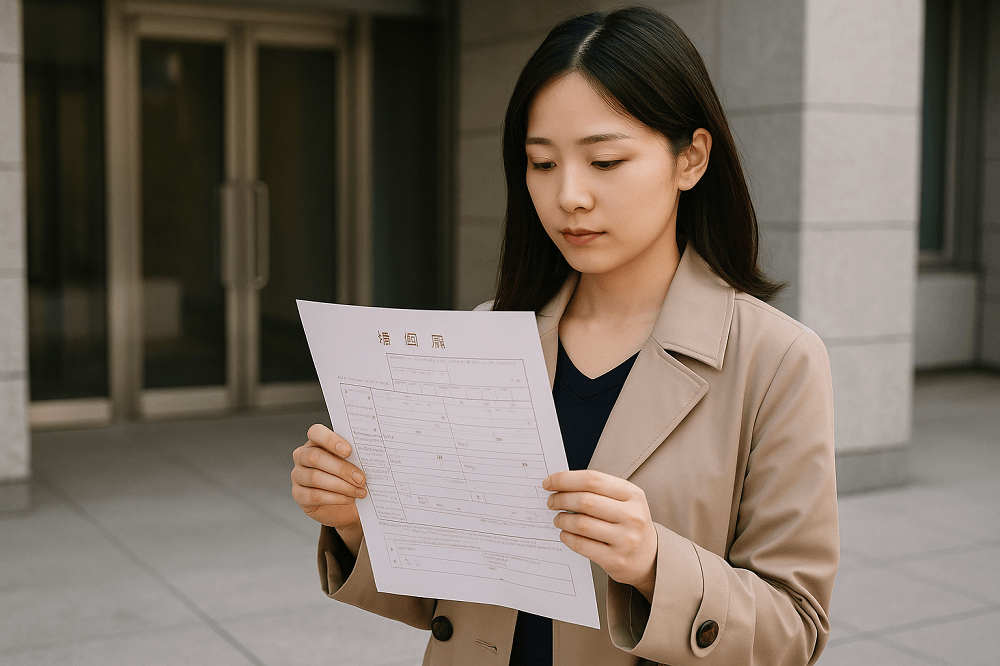
婚姻届をひとりで出すことの背景
パートナーの仕事の都合、遠距離恋愛、プライベート重視のスタイル、または結婚そのものに対する価値観の変化など、現代における多様なライフスタイルが影響し、婚姻届をふたり揃って提出できないケースが増えています。さらに、デジタル社会の中で「一緒に役所へ行く」という形式的な行為よりも、効率や合理性を優先するカップルも増加傾向にあります。また、コロナ禍以降は接触を避ける目的やスケジュール調整の困難さから、あえてひとりで手続きを済ませる人も見られるようになりました。
婚姻届をひとりで出す人の割合
総務省や自治体の発表では正確な統計は出ていないものの、複数のウェブアンケートやSNS上の投稿を参考にすると、全体の約3割〜4割程度が「ひとりで提出した経験がある」と回答しており、想像以上に多くの人がこのスタイルを選んでいることがわかります。特に都市部では割合が高い傾向があり、共働き世帯や個人主義を重んじる傾向が背景にあると考えられます。
統計データから見るひとりでの婚姻届提出
婚姻届の提出時にふたりが揃っている必要はなく、提出自体はどちらか一方でも問題ありません。そのため、自治体による正確なデータ取得は難しく、実際の窓口でも「誰が提出したか」に関する記録は残されていないことが多いです。しかし、自治体職員へのヒアリングや現場での聞き取り調査を通じて、「ひとりで提出するケースは週に数件から十数件にのぼる」との声もあり、一定の割合が現実的に存在することが伺えます。また、最近では役所内の職員が「提出はおひとりで?」と尋ねることもあり、これが今後の統計データ収集に活かされる可能性もあります。
婚姻届をひとりで出す理由

ひとりで出すことのメリットとデメリット
【メリット】
- スケジュール調整が不要:ふたりの予定を合わせる必要がないため、空いている時間に手軽に提出できる
- 手続きがスムーズ:事前に書類を整えておけば、窓口では数分で完了することも多く、待ち時間や移動の負担が軽減される
- 感染症対策としても有効:混雑を避けて個別に行動することは、健康面の配慮にもつながる
【デメリット】
- 記念感が薄れる:ふたりで提出するというイベント性がなくなり、思い出が薄くなってしまうという声もある
- 書類不備時の再提出が必要になる可能性:その場で訂正できない場合、再度ふたりで確認する手間が発生する
- 説明を聞く際にパートナーがいないことで不安が増すケースも
結婚式をしないカップルの選択肢
結婚式や披露宴を行わないカップルにとって、婚姻届提出は唯一のセレモニー的なイベントです。フォトウェディングや記念撮影のみを選ぶカップルも多く、提出という形式的な行為に過度な演出を加えずに「ひとりで淡々と済ませる」ことが合理的だと考える人もいます。また、記念日は提出日とは別にふたりで設定し、日常の中でお祝いするというスタイルも選ばれています。
ひとりで出すことを選ぶ心理背景
「自分たちらしさを大切にしたい」「相手に負担をかけたくない」「できることは分担して効率よく進めたい」といった理由から、主体的にひとり提出を選ぶケースも見られます。特に、結婚に対して実用的な考えを持つ人や、共働きで忙しいカップルに多く見受けられます。また、同性カップルや事実婚カップルの中にも、書類提出そのものに感情を込めないスタイルを選ぶ傾向があるようです。
婚姻届ひとりで出すために必要なもの

婚姻届提出に必要な書類一覧
- 婚姻届(記入済み)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(本籍がある自治体以外に提出する場合)
- 住民票(必要な場合)
- 印鑑(シャチハタ不可。ふたり分あると安心)
- 提出先の役所の所在地メモ(迷わず行くために事前確認)
これらの書類は、提出する役所によって必要・不要が異なることもあるため、できれば事前に電話や公式サイトで確認しておくのがおすすめです。
証人や印鑑の準備の重要性
婚姻届には20歳以上の証人2名の署名と押印が必要です。証人は親族でなくてもかまいませんが、日本国籍を持ち、成人していることが条件です。署名・押印は事前に済ませておく必要があり、提出当日にその場で用意することはできません。また、証人欄に不備があると受理されないため、事前にしっかり内容を確認し、記入後にもう一度チェックすることが大切です。印鑑の種類も要注意で、シャチハタではなく、朱肉を使うタイプの印鑑を使用するようにしましょう。
住民票や戸籍謄本の取り扱い
住民票の移動や新戸籍の作成が必要になるケースもあるため、婚姻届の提出前後に必要な手続きを把握しておくことが重要です。たとえば、ふたりの本籍地が異なる場合は、戸籍謄本が必要になります。また、結婚後に氏が変わる場合は、運転免許証や保険証、銀行口座などの名義変更手続きにも住民票や戸籍謄本が求められることがあります。提出後の手続きがスムーズに進むよう、複数部用意しておくと安心です。
婚姻届をひとりで出す方法

婚姻届の書き方を解説
誤記や漏れがあると受理されないため、事前に書き方ガイドを参照し、すべて記入済みかチェックしましょう。婚姻届は法的効力を持つ重要な書類のため、ちょっとしたミスが受理不可の原因になります。特に、氏名や本籍地の記入方法、証人欄の書き方などに細心の注意が必要です。自治体によってはサンプル記入例やオンラインでの記入サポートを提供していることもありますので、積極的に活用しましょう。書き方の不安がある場合は、事前に役所へ行って確認したり、電話やメールで問い合わせてアドバイスをもらうのもおすすめです。
提出先の役所での手続き
婚姻届は本籍地、所在地、もしくは一時的な滞在地の市区町村役場に提出可能です。提出の際には、本人確認書類を窓口で提示する必要があります。記載内容に不備がなければその場で受理され、受理証明書の交付も依頼できます。役所によっては夜間・休日窓口での受付も可能な場合があり、仕事などで平日に行けない人にとっては便利な制度です。ただし、夜間受付ではその場での確認作業が行われず、後日不備の連絡が入る可能性もあるため、注意が必要です。
提出前のチェックポイント
- 記入漏れがないか(すべての欄に正確に記載されているか)
- 証人欄が正しく書かれているか(署名・押印ともに2名分揃っているか)
- 捺印が必要な場所に押印されているか(シャチハタではなく朱肉を使用した印鑑か)
- 修正がないか(訂正は原則不可なので書き損じがあれば新しい用紙に書き直す)
- 添付書類が揃っているか(戸籍謄本や本人確認書類など)
これらのチェックを行ったうえで、万全の準備をして役所に向かうことで、スムーズな提出が可能になります。
提出前に確認すべき注意点

記入時の注意事項
ボールペンで記入し、訂正は原則認められていません。必ず黒または濃い青のインクを使用し、消せるボールペンや鉛筆での記入は避けてください。記入ミスをしてしまった場合、修正液や修正テープを使うこともNGとされており、新しい用紙に改めて記入する必要があります。予備の婚姻届を数枚用意しておくと、書き直しの際も安心です。また、記入中に不安がある場合は、無理に進めず、役所や書類見本を参照して慎重に進めましょう。
誤りを避けるための準備
誤記や漏れを防ぐには、役所が配布している記入見本や公式サイトの記入例を参考にするのが効果的です。とくに本籍地や続柄、証人欄などは間違えやすいため、見本を見ながらひとつずつ丁寧に記入しましょう。また、記入後はパートナーや証人と一緒に内容を確認するのがベストです。第三者の目を通すことで、自分では気づけなかったミスを早期に発見できる可能性があります。記入に慣れていない場合は、予行演習として一度下書きをしてみるのも良い方法です。
提出後の流れと注意点
婚姻届が無事に受理されると、「受理証明書」や「婚姻届受理通知書」が発行される場合があります。これらの書類は、パスポートや銀行口座の名義変更などに使用できるため、必要に応じて取得しておきましょう。また、結婚にともなう住所変更や健康保険・年金手続きも忘れずに行いましょう。さらに、名字が変わる人は、運転免許証・クレジットカード・職場への届け出など、多岐にわたる変更作業が必要になります。役所での婚姻届提出が完了しても、それが終わりではなく、結婚後の生活に向けた一連の準備がスタートするという意識を持っておくことが大切です。
ひとりで出す際の不安と対策

不安を解消するための準備
- 必要書類のチェックリストを作成
- 婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などを事前に一覧化し、チェックマークをつけていくことで、漏れなく準備できます。スマホのメモアプリや紙のリストにまとめておくと便利です。
- 事前に役所に問い合わせて確認
- 受付時間、必要書類の内容や条件、休日受付の可否などを電話や公式サイトで確認しておくと、当日の不安が軽減されます。特に戸籍謄本の要否や、提出後の処理に関する情報は見落としがちなので注意しましょう。
- 書類提出時に何を伝えるか、どのような流れになるかを簡単にイメージトレーニングしておくと、スムーズに対応できます。
ひとりで出すことによる影響
心理的な寂しさを感じる人もいますが、しっかり準備すれば達成感も得られます。特に、自分ひとりで大切な手続きを終えることで、自立したパートナーシップへの意識が高まるという声もあります。また、ひとりで提出することで結婚という制度への理解がより深まり、ふたりの間で改めて関係性を見つめ直す機会になることもあります。逆に、形式や儀式性を重んじる人には物足りなさを感じさせる側面もありますが、それもひとつの気づきとしてポジティブに捉えることができます。
トラブル時の対処法
不備があった場合はその場で修正できないため、再度出直す必要があります。記入漏れや印鑑の不備、証人欄の記入ミスなどは非常に多いトラブルの一つです。これを防ぐためには、提出前に第三者に確認してもらう、チェックリストを使って自己点検を徹底することが重要です。また、もし不備が発覚した場合は、焦らず役所の指示を仰ぎ、必要書類を持ち帰って冷静に再準備を行いましょう。役所が混雑していない時間帯を狙うことで、職員にも相談しやすく、再提出の際にも安心です。
婚姻届提出にかかる時間

役所での婚姻届受付時間
一般的に役所の婚姻届受付時間は平日9時〜17時が基本ですが、自治体によっては時間外窓口や休日受付の制度を設けているところもあります。特に24時間受付ボックスが設置されている市区町村では、夜間や早朝でも提出が可能です。ただし、時間外に提出された場合は即時に内容確認が行われず、後日職員によるチェックで不備が見つかった場合は再提出が必要になるケースもあります。そのため、時間外受付を利用する場合は、提出書類の記入ミスや不備に特に注意が必要です。また、提出後すぐに受理証明書などを受け取りたい場合は、平日昼間の提出が確実です。
スケジュールに合わせた提出のコツ
混雑を避けたい場合は、役所が比較的空いている時間帯を狙いましょう。午前10時前や午後の昼過ぎ(14時〜15時頃)は比較的来庁者が少なく、窓口対応もスムーズなことが多いです。また、月初めや月末、祝日直前・直後は混雑が予想されるため、避けたほうがよいでしょう。月の中頃の平日は比較的空いている傾向があり、落ち着いて手続きをしたい方におすすめです。もしふたりの都合が合わない場合は、仕事前後や昼休みなど、自分の生活リズムに無理のない時間帯を見つけることも大切です。
祝日や混雑時の対応
祝日、大安、語呂の良い日(例:11月22日=いい夫婦の日)などは、婚姻届の提出が集中しやすく、特に人気のある日には長蛇の列ができることもあります。ゴールデンウィークや年末年始は自治体の営業日が限られるため、混雑のピークに注意が必要です。どうしてもその日に提出したい場合は、開庁時間前から早めに到着しておくのがおすすめです。また、夜間や休日の時間外受付を利用する場合は、提出後の確認が遅れる可能性を見越して、時間に余裕をもって行動しましょう。事前に役所のHPや電話で混雑状況を確認しておくと、安心して当日を迎えることができます。
ひとりでの婚姻届提出に関するアンケート結果

カップルの割合と選択理由
「仕事の都合で同時に行けなかった」「提出するのが苦手なので相手に任せた」「役所が遠方だったので手分けした」「少し照れくさかった」など、理由は実にさまざまです。中には「結婚に関してドライな考え方をしているから」「普段から手続きは自分が担当しているため」といった実務的な理由を挙げる人もいれば、「結婚という制度そのものに対して特別な感情を持たないから」と語るケースもあります。ひとりで婚姻届を出すという行為は、形式や習慣に縛られず、現代的な価値観に基づいた選択のひとつとも言えるでしょう。
世帯主としての意識の変化
ひとりで提出することで、「家族をつくる第一歩」としての責任感が芽生える人も少なくありません。特に、書類を自らの手で提出し、受理の瞬間を経験することで、「自分たちはこれから家族として歩んでいくのだ」という自覚が強くなるという声もあります。また、提出を任された側が家族代表としての意識を高めるきっかけになったり、自立した夫婦関係の始まりとして肯定的にとらえる人も増えているようです。中には「結婚式よりも現実的で印象深かった」と話す人もおり、書類提出そのものが象徴的な出来事になることもあります。
実際の体験談や声
「意外とあっさり終わった」「書類が多くて緊張した」「窓口の方が優しくて安心した」「写真でも撮ればよかった」「意外と感動した」など、リアルな声もSNSで多数見受けられます。特に印象的なのは、「提出した瞬間に“これで結婚したんだ”と実感した」という体験談です。反対に、「もっとドラマチックな瞬間かと思ったけど、あっけなかった」という意見もあり、人それぞれ感じ方に差があることがわかります。また、提出時に婚姻届をコピーして記念に取っておく人や、提出前にツーショット写真を撮るなど、ひとり提出でも工夫して思い出づくりをするカップルも増えています。
これからの婚姻届提出スタイル
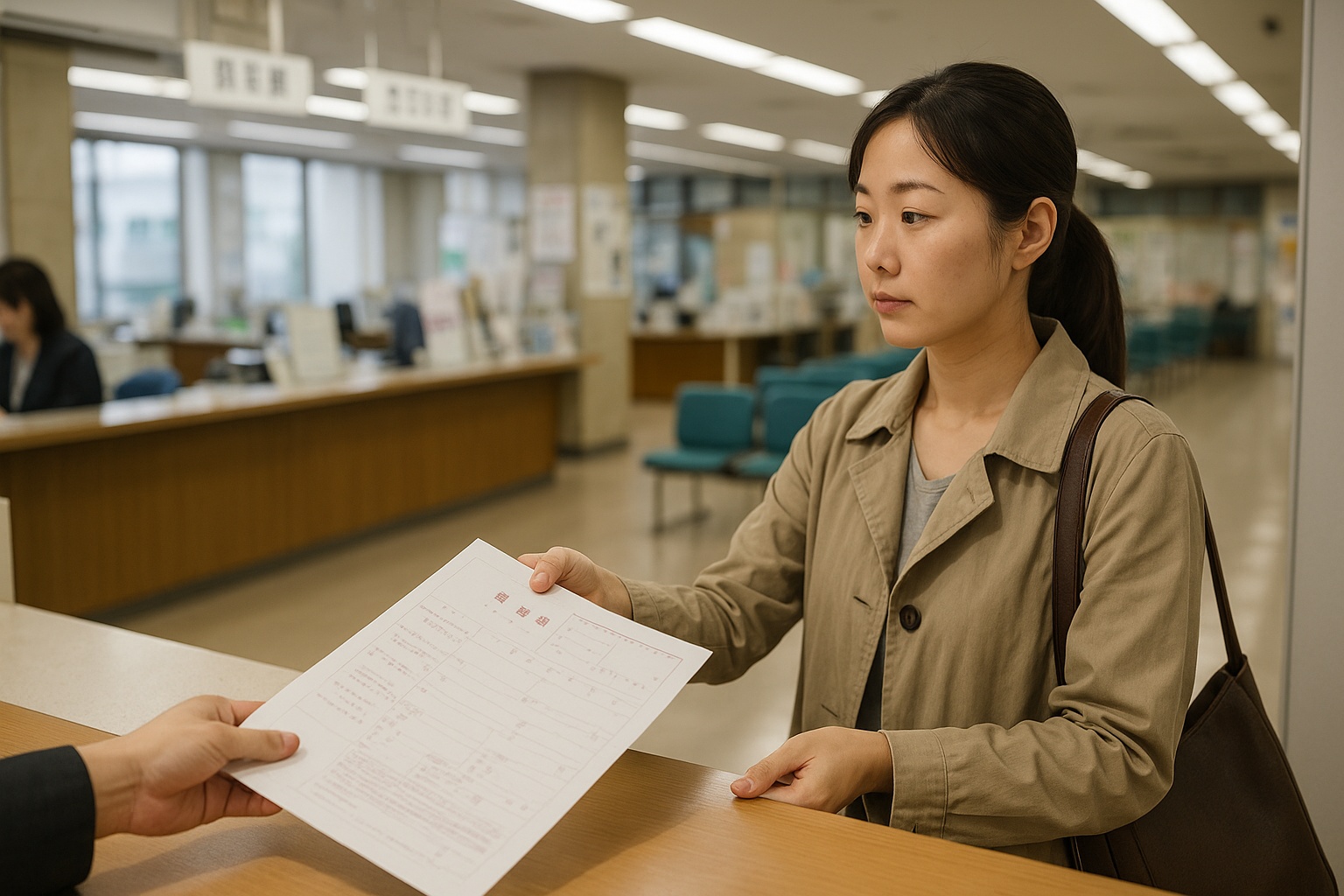
ひとりで出す婚姻届の増加傾向
ライフスタイルの多様化により、今後もこの傾向は続くと見られています。共働きの増加や遠距離恋愛の普及、結婚に対する価値観の多様化などが背景にあり、婚姻届を「ふたりで同時に提出する」という従来の形にこだわらない人が増えています。また、スマートフォンやSNSの普及により、提出の様子を写真や動画で共有するなど、物理的に一緒にいなくても気持ちを共有できる手段も広がっています。その結果、形式にとらわれず、自分たちにとって無理のない方法を選ぶ人が今後さらに増えていくと予想されます。
新たな結婚生活のスタート
形式にとらわれない婚姻届の提出も、新しい夫婦の在り方として注目されています。結婚式や披露宴といったセレモニーをあえて行わず、静かに家庭生活をスタートさせたいと考えるカップルや、必要最低限の手続きのみにフォーカスするミニマル志向のカップルも増加傾向にあります。また、ライフステージやパートナーとの関係性に応じて、あえて一緒に提出することを避けるという選択もあり得ます。こうした価値観は、今後の結婚観にも大きな影響を与えていくでしょう。
夫婦としての未来について
婚姻届提出のスタイルは違っても、夫婦生活の充実に向けた第一歩であることに変わりはありません。大切なのは、どのような形であっても互いに納得し合い、尊重し合いながら家庭を築いていくことです。提出の方法に正解はなく、それぞれの夫婦にとってベストな形を選ぶことが大切です。むしろ、ひとりで提出したことが話のネタになったり、後から思い返したときに特別な思い出になることもあります。結婚生活において何を大切にしたいかを考えるきっかけとして、婚姻届提出という小さな儀式が果たす役割は意外と大きいのかもしれません。
まとめ
婚姻届をひとりで出すことは、今や珍しいことではありません。ライフスタイルの変化や働き方の多様化、価値観の柔軟化によって、結婚という一大イベントの形もさまざまに変わりつつあります。ふたりで一緒に提出することにこだわらず、効率や事情に応じて一方が代表して提出するという形が、むしろ現代的で合理的な選択肢のひとつとして定着しつつあるのです。
大切なのは、ふたりでしっかり話し合って、その形を選んだことに納得し合うこと。婚姻届の提出は、法律的な手続きであると同時に、ふたりが新しい生活に踏み出す最初の一歩でもあります。その手段が「一緒」か「ひとり」かという形式に縛られる必要はありません。
むしろ、自分たちのペースや状況に合った方法を選ぶことこそが、これからの夫婦の在り方を象徴するものになるはずです。形式にとらわれず、自分たちらしい結婚の形を大切にしながら、新たな人生を歩み始めてください。

